Comprehensive Dental Checkup
歯科ドッグ
お口の健康状態を総合的にチェックする
予防プログラム

歯科ドックとは、精密な検査によってお口の健康状態を総合的にチェックする予防プログラムです。
歯や歯ぐきの状態はもちろん、唾液検査・細菌検査などを通して、虫歯や歯周病などの疾患を初期段階で発見・予防することを目的としています。
もし異常が見つかった場合には、適切な処置を早期に行うことで、一生涯ご自身の歯で快適に食事を楽しみ、健康的な毎日を送るサポートをいたします。
欧米ではすでに、定期的な歯科ドックが人間ドックと並ぶ健康管理の一環として定着しており、日本でも健康意識の高い方々を中心に注目が高まっています。
お口のリスクは人それぞれ異なります。
そのリスクを症状が出る前に知り、対策することこそが最良のケアです。
“治す”のではなく“守る”ためのメンテナンス──それが、歯科ドックです。
こんな方におすすめ
お口の状況を把握し、今からしっかりメンテナンスしておきたい
病気のかかりやすさは、人それぞれです。
そのため、どれくらいの頻度でメンテナンスが必要なのか、日頃から何に気をつければよいのかも個人差があります。
当院では、歯科ドックの結果を基に、患者さまの状態にあったオーダーメイドの治療計画を立案いたします。

虫歯、歯周病になる可能性があるか知っておきたい
重度の虫歯や歯周病を患った場合、痛みや出血によって、自覚症状が出てきます。
しかし、初期段階の虫歯や歯周病は、自分ではなかなか気づくことができません。
歯科ドックでは、初期段階の虫歯、歯周病を早期発見し、症状の重症化を防ぎます。

歯科ドッグの特徴
1.
様々な精密検査でお口の健康を医学的に分析
当院の歯科ドックでは、スタンダードプラン、歯周病細菌検査セットプランの2種類のプランをご用意。通常の定期検診では発見が難しい症状も、豊富な精密検査によって早期発見へと導きます。
2.
保険診療では分からないところまでしっかり診察
メニュー内には、唾液検査・細菌検査や歯の模型作成・咬み合わせの診断など豊富な精密検査が組み込まれています。今ある虫歯・歯周病などの疾患だけではなく、簡易的な歯科検診では発見が難しい将来のリスクに至るまで、細かく診断いたします。

歯科ドッグの流れ
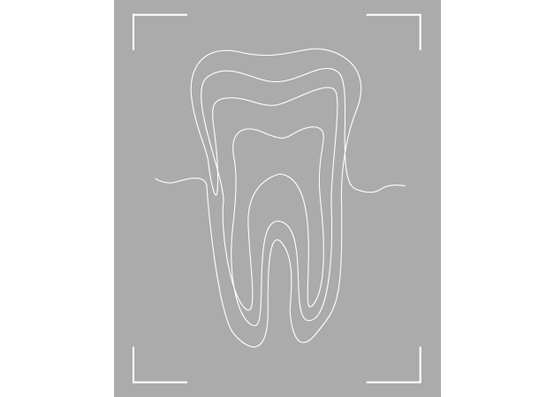
エックス線写真診査
- レントゲン写真
まず初めに、エックス線写真による診査を行います。
肉眼では確認できない歯や骨の内部構造を映し出すことで、お口全体の状態を正確に把握することができます。
代表的な撮影法には、歯1本1本を細かく観察できるデンタルエックス線写真(10~14枚法)と、上下のあごの骨を1枚に収めて全体像を確認できるパノラマエックス線写真があります。
これらを組み合わせることで、より正確な診断と治療計画の立案が可能になります。
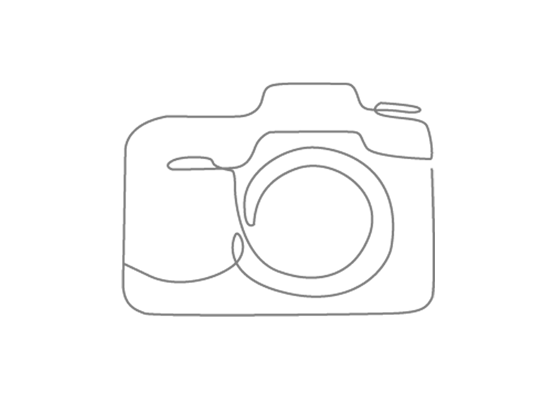
口腔内写真撮影(視診)
- 口腔内写真撮影
お口の健康状態を正確に把握し、どのような治療が最適かを診断するために、まずは口腔内写真を撮影します。
虫歯の有無はもちろん、過去の治療跡や現在の詰め物・被せ物の状態、歯の位置関係やすり減り具合などを目視で丁寧に確認します。
このように、直接お口の中を観察することを歯科では「視診」と呼びます。
撮影したお写真は、お口の状態を視覚的にわかりやすく共有できる資料として、治療方針の説明にも活用します。
患者さまご自身にも、変化や改善の様子を一緒に確認していただけます。
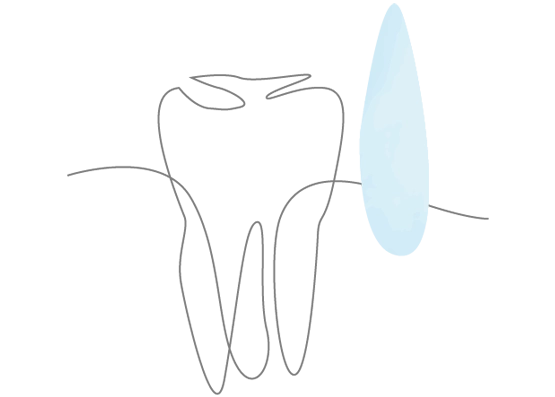
唾液検査
- 唾液検査
唾液の量と質(緩衝能)を調べる検査です。
唾液には、食べかすや細菌を洗い流したり、歯を保護したりする働きがあります。
分泌量が少ないと、これらの作用が弱まり、虫歯や歯周病のリスクが高くなる傾向があります。
また、唾液の「緩衝能」は、口の中が酸性に傾いたときに中性に戻す力のことです。
この力が弱いと、虫歯になりやすくなります。
唾液検査は、お口の健康リスクを数値で把握できる大切な検査です。
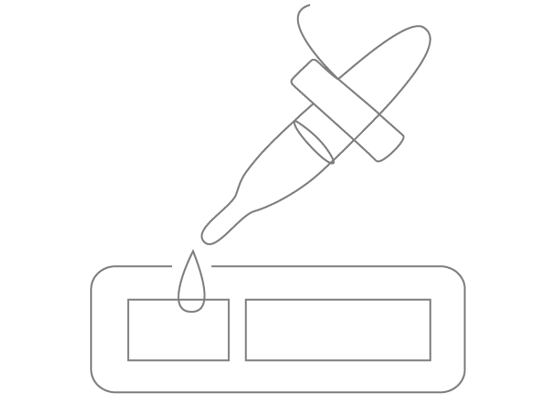
虫歯細菌検査
- 虫歯菌検査キット
虫歯の発症に関わるミュータンス菌とラクトバチラス菌の数を調べる検査です。
ミュータンス菌は、食べ物や飲み物に含まれる糖分を栄養に増殖し、歯の表面に付着して酸を作り出すことで虫歯を発生させる菌です。
一方、ラクトバチラス菌は、すでにできた虫歯の中で増え、虫歯を進行させる菌とされています。
これらの菌の量を調べることで、虫歯になりやすさや食生活の傾向を客観的に把握することができます。
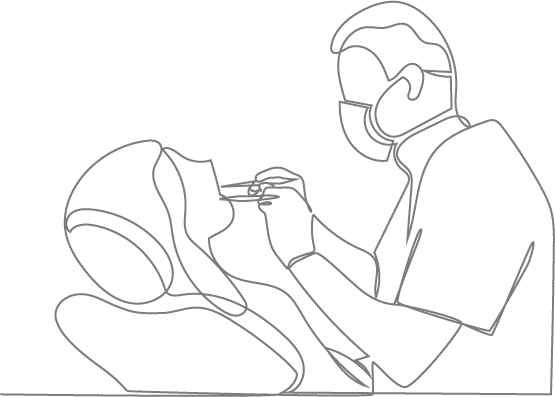
口腔内の検査
- 視診・触診
ずは、お口の中を目で見て、触れて確認する視診・触診を行います。
進行中の虫歯や歯周病がないかをチェックし、治療が必要かどうかを診査します。
あわせて、過去に治療した歯の詰め物や被せ物の適合状態も確認します。時間の経過により、材質によっては劣化や欠け、浮き上がりが見られる場合があります。
さらに、舌・頬・粘膜などの状態を観察し、口腔がんや感染症の早期発見にもつなげます。
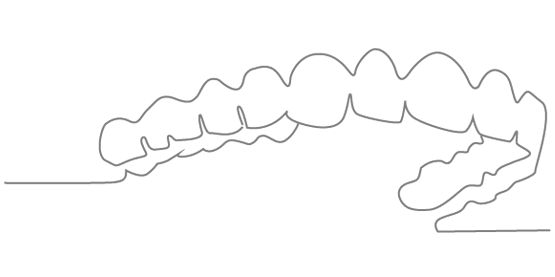
歯列模型作成
- 模型作成
歯列模型(スタディモデル)を作成し、口腔内を評価します。
実際の口腔内では見えにくいところであっても、歯列模型を作成することで、多方向から評価することができます。
また、細かく数値を計ることも可能になるため、平均値と照らし合わせた客観的な計測をおこなうことが可能です。
例えば、歯並びのような静的(解剖学的形態)な情報だけではなく、噛み合わせや歯ぎしり、噛みしめなど動的な情報も得ることができます。
お口全体の健康を守るための、基本かつ重要な診査です。
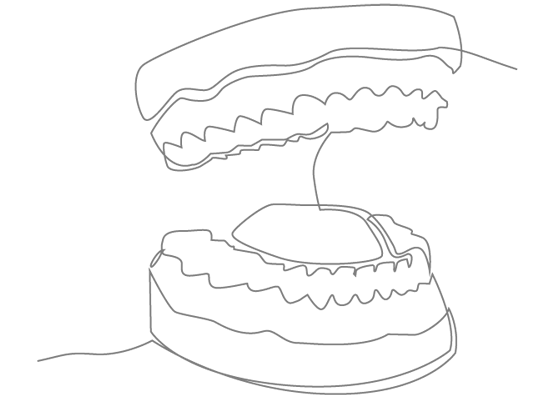
咬み合わせ診断
- 視診・触診
上顎と下顎を噛み合わせること「咬合(こうごう)」といいます。
この咬合のバランスが崩れていると、歯や歯周組織、顎関節などのどこかに負担がかかり、結果として歯周病・歯の欠損・顎関節症など、さまざまなトラブルを引き起こす原因になります。
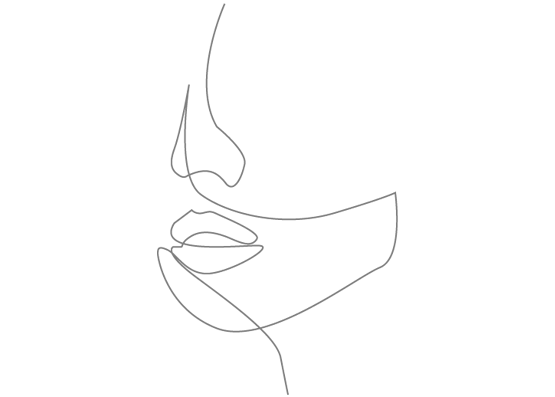
審美診断
- 視診・触診
「スマイルライン」や「Eライン」という言葉を耳にしたことはありますか?
これらは、お顔の各パーツの位置関係やバランスを表す、美しさの基準となるラインです。
スマイルラインとは、口角を上げて笑ったときに見える上の前歯の先端を結んだ線のことを指します。このラインが下唇のカーブに沿っていると、笑顔がより美しく見えると言われています。
一方、Eラインは横顔で見たときの鼻先とあご先を結ぶラインのことです。上下の唇がこのライン上、もしくは少し内側にあると、横顔が整って見えるとされています。
審美診断では、歯の位置関係や口を開いたときにどの程度歯や歯茎が見えるかなどを、計測・視診・触診によって確認します。
スマイルラインやEラインといった基準と照らし合わせながら、現在の状態を診断し、わかりやすくご説明いたします。
また、ご希望があれば、理想的なバランスに近づけるための治療方法もご提案いたします。
歯周病細菌検査セットプラン
スタンダードプランに、歯周病の感染リスクを検査する歯周病細菌検査をプラスしたセットプランです。
従来の歯周病検査では、歯周ポケットの深さや歯肉の炎症などの歯周組織の破壊状態を形態的に調べることが中心でした。
しかし、当院では予知性の高い治療と予防を展開すべく歯周病の細菌検査も併せてご用意しております。
【歯周病細菌検査】
歯周ポケットから採取した検体を検査に出し、歯周病の原因菌を数値で確認します。
歯周病の原因菌には、歯周病の悪化に最も関連性が高いと考えられているレッドコンプレックスと呼ばれる3つの細菌があります。
<歯周病の発症の原因と考えられているレッドコンプレックス>
・Pg菌(Porphyromonas gingivalis)※特に毒性の強い歯周病菌
・Tf菌(Tannerella forsythensis)
・Td菌(Treponema denticola)
これらの細菌の数を数値化することで、現在、歯周病になっているかを診断します。また、現在は歯周病を発症していない場合も、細菌の量を参考にし、リスクの高さを評価することができます。

【オプション】CT診断
最新鋭の歯科用CTによって、より精度の高い検査を素早く実施できます。
病院のCTのように、身体を輪切りにしたような画像を撮影する断層撮影の原理を用いますが、歯科用CTはより高解像度で撮影できます。
そのため、歯や骨をより詳細に見ることができ、視診だけでは見えない部分までを可視化することができます。
【歯周病治療】
歯周病を発症している場合、どのくらい骨が溶けてなくなってしまっているかをCTで確認できます。骨が溶けている状況次第で、治療方針が変わってきます。
【インプラント治療】
骨の高さや幅、形態を確認し、神経や血管を避けて安全にインプラントを埋め込むことができるかを診断できます。
【根管治療】
歯の根(根管)の数や向きを確認できます。治療の前に、根管の情報を把握することで、精度の高い診断とスムーズな治療が可能になります。
【親知らずの抜歯】
神経の近くにある親知らずの抜歯はリスクを伴います。
下顎では、神経と親知らずの位置関係を事前に把握することで、神経を傷つけるリスクを大きく下げることができます。
上顎では、上顎洞と呼ばれる鼻から繋がる副鼻腔に近接していることがあります。抜歯の際に副鼻腔と口腔内が繫がってしまうケースもあることから、上顎洞の交通の危険性も判断が可能です。
【副鼻腔炎(蓄膿症)】
鼻の周りに多数存在する鼻腔と通じる空洞のことを副鼻腔と言います。この副鼻腔が慢性的に炎症を起こしている状態が、慢性副鼻腔炎=蓄膿症です。
CTでは副鼻腔に膿が溜まっているかを確認できるので、蓄膿症の早期発見が可能です。
さらに、蓄膿症は歯に問題がある場合と、風邪等で鼻炎を起こしたことが原因の場合があります。
歯に問題がある場合、副鼻腔に歯の根が貫通していることが多いのですが、CTではその関連性も確認ができます。
よって、蓄膿症の場合、歯科で治療する必要があるのか、耳鼻咽喉科で治療する必要があるのかを診断できます。歯に問題はなく歯科で治療する必要はない場合、専門の病院をご紹介いたします。
歯科ドックの費用
- スタンダードプラン
- ¥49,500
- 歯周病細菌検査セットプラン
- ¥77,000
- CT診断オプション
- 上記いずれかのプランに追加 ¥16,500
